Grabで気になった「コムタム・ロンスエン」
Grabで食事をデリバリーしているときに、目にとまったのがCơm Tấm Long Xuyên(コムタム・ロンスエン)
普段からよく食べるコムタムだけど、「ロンスエン式」と書かれているのが気になった。
もしかして、これがコムタムの発祥なんじゃないか?
そう思ったら気になって仕方がなくなり、オーダーして比べてみることにした。
デリバリーで食べ比べてみた
タオディエンのNam Nam Kitchen
左が「コムタム・ロンスエン」、右が「コムタム・サイゴン式」

- ロンスエン式 → 具材が細かくカットされていて混ぜやすい
- サイゴン式 → 大きなポークチョップが豪快にのっている
見た目からして、両者のスタイルの違いがはっきりわかる。
実際に食べると、ロンスエン式はすべての具材がご飯に絡みやすくて食べやすい。サイゴン式の“肉をガブっと”という迫力とはまた違う魅力だ。
ロンスエン専門店のデリバリー
次は、近所の Cơm Tấm Long Xuyên – Cô Su からデリバリー。
ここはロンスエン式を看板にしている専門店。
具材はやはり細かくカットされていて、ご飯の粒も小さい。

食べ進めると「米が細かい」という特徴がよくわかる。これがロンスエン式のこだわりで、口に運ぶたびに具材と一体化して混ぜやすい。
「コムタム」の発祥を調べてみた
ここで一度、「そもそもコムタムの発祥はどこなのか?」を徹底的に調べてみた。
- サイゴン発祥説が最有力
- 19世紀末、タウフー運河沿いのビンヨン米倉で働く労働者が、精米で出る「割れ米=tấm」を食べ始めた
- 1920年代には労働者向けの料理として販売されていた記録がある
- 1940年代には「皿飯(cơm dĩa)」文化に組み込まれ、豚カツレツや卵と合わせるスタイルが登場
- 戦後〜1970年代にかけて、サイゴンの名物ストリートフードとして全国に広まった
- ロンスエンの位置づけ
- 米どころとして「割れ米食文化」が根付いていた土地
- 「具材を細かく刻む」「混ぜやすい」「米粒をさらに小さく」という独自進化を遂げ、ご当地版のコムタムとして定着
- 2023年には「アジア記録Top 50」に認定され、観光資源としてもブランド化
つまり、発祥はサイゴン。
ロンスエン式は発祥ではなく、進化系ご当地バージョンだった。
実際に店舗へ行ってみた
発祥ではないとわかったけど、「皿で食べておきたい」と思い、翌日は実際にお店に足を運んだ。
訪れたのは、前日にデリバリーを頼んだ Cơm Tấm Long Xuyên – Cô Su


陶器の皿に盛られたコムタムは、デリバリーよりもさらに美味しそうに見える。
ヌックマムをかけて混ぜると、細かく刻まれた具材と割れ米がよく絡み、全体が一つの料理としてまとまっていく。


食べていて感じたのは、サイゴン式の「豪快さ」とは対照的な、“まとまりのある食べやすさ”こそがロンスエン式の真骨頂だということ。
店の前には大きく「Cơm Tấm Long Xuyên」と掲げられ、30K(約180円)という庶民価格。
ローカル食堂の空気の中で食べると、ロンスエン式の魅力がより一層伝わってきた。
まとめ
- コムタムの発祥はサイゴン(ホーチミン市)が最有力
- ロンスエン式は発祥ではないが、具材を細切り・米粒を小さくして混ぜやすくした“ご当地進化型”
- デリバリーで食べ比べても違いはわかったが、実際に店舗で皿で食べるとロンスエン式の本領がはっきり感じられた
結論として、ロンスエンまで行く必要はないけど、ホーチミン市内で“ロンスエン式”を試す価値は十分にある。
サイゴン式の豪快さと、ロンスエン式のまとまり感。どちらにも良さがある。
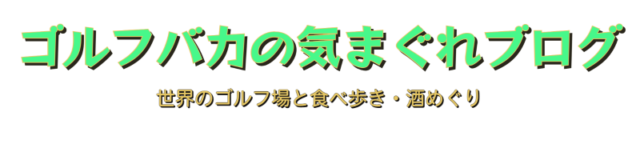



コメント